skip to main |
skip to sidebar
「もしも実在というものが、誰の感性や意識とも直接にふれることができるものなら、詩というものなどはいらないだろう。いやそのとき、ぼくらすべては詩人になるはずである。しかし実際には、ぼくらはどんな実在をも見てはいないのだ。ぼくらが見たり、きいたりするものは、単にぼくらの功利的行為の手先として、もろもろの感覚がえらんでくれたものにすぎない。実在の本質のうち、実際にぼくらの実用に役立つもの以外は、ことごとく抑圧されてしまっているのである。知覚のはたらきは、或る型にはまって、事物は初めから、ぼくらにどう利用できるかを目当てに分類されてしまっているのだ。ぼくらが知覚するのは、事物の真相ではなくて、むしろこの分類なのだ。ぼくらは事物の相をみるのではなくて類型を見るにすぎないといわれる。こうして人間意識の類型化は、文明がその物質的条件で、ぼくたちを圧迫すればする程、その度合は進んでいく。かくして「存在忘却の夜」は深まっていくのである。」詩集〈亡羊記〉 「後書」 より
「村野四郎詩集」 思潮社 収録

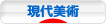 にほんブログ村
にほんブログ村 にほんブログ村
にほんブログ村


0 件のコメント:
コメントを投稿